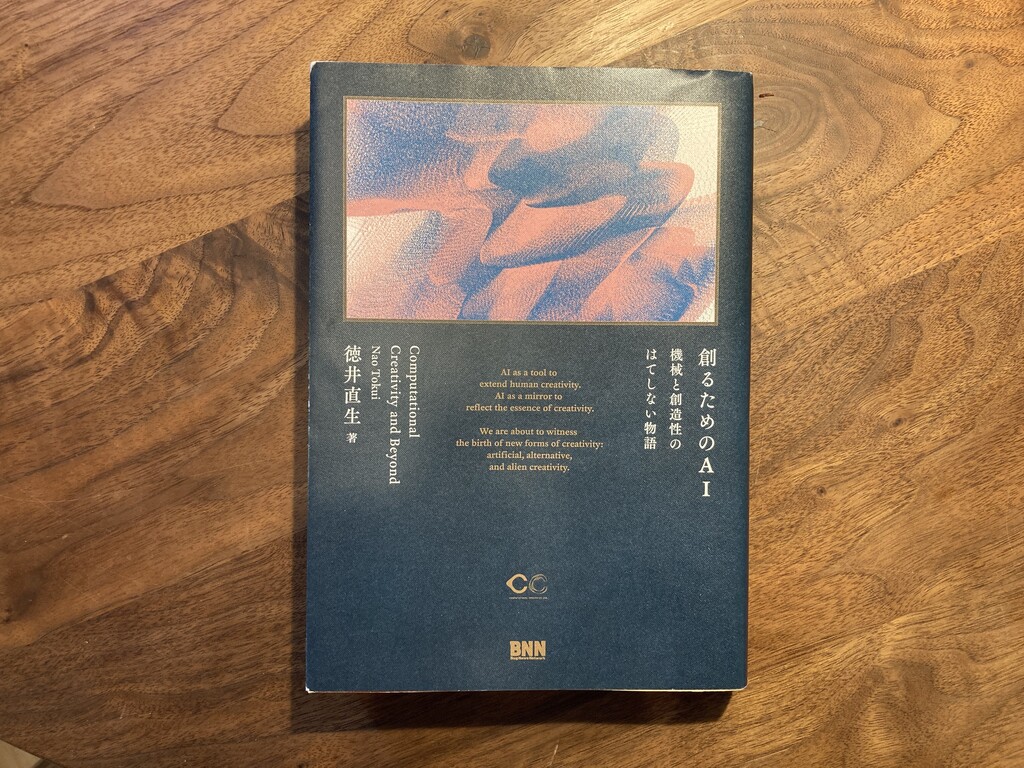『創るためのAI 』は、ジャンルによらず表現にかかわるすべての人におすすめしたい本だ。本書は、AI(人工知能)と人間の創作のかかわりを、多くの歴史や事例をまじえながら丁寧に解説している。現在のAIブームを引き起こした深層学習(ディープラーニング)の要点も紹介されている。先端技術がテーマだが、柔らかな語り口ですらすらと読める。
著者の徳井直生は、国内外に活躍するアーティストで、クリエイティブチームQosmoを設立し、慶應大学では研究・教育にあたっている。日本でAIアートを実践するトップランナーの一人だ。
AIによる表現は是か非か
このところ、世の中ではAIが大きなブームになった。AIは2010年代以降、技術的な飛躍とともに大きな注目をあびている。社会活動のあらゆる領域でAIの活用や置き換えが進むと、将来人間の仕事が奪われると予測する脅威論があふれた。一方で、AIには人間のような賢さはなく役に立たないと軽視する論調もあり、評価が揺れ動いている。
表現の分野でもAIの評価は二分している。まるで創作しているようなAIのニュースは数多く飛び交っている。AIが「本物のような絵画」を描いて高値で取り引きされ、「人間が書いたような小説」を書き、故人となった「歌手の歌声で歌った」などだ。こうした出来事から、AIを「超人的な創作者」と考える人がいれば、人間を冒涜する「モノマネ」や「単なる道具」に過ぎないと断じる人もいる。いったいどちらが正しいのだろう。著者は双方の見方のあいだに存在するグラデーションに着目することで、人間の創造や創造性を再考するヒントを得ることができ、創造性を拡張できると呼びかけている。
このように本書のAI観は、脅威論にも軽視論にもくみせず、バランスがとれている。AIによるバラ色の未来を語ることも、不安を煽ることもしない。全体的に希望に満ちたトーンで貫かれてはいるが、新しい技術をただ礼讃してはいない。AIのバイアスや倫理的問題にも触れ、悪影響にも目を配っているからだ。AIをつかった表現では、特定のスタイルやパターンが強化されてしまったり、創作の主体がわかりにくくなったりする問題があるという。
表現を〈更新〉した機械の歴史
AIによって創作が再定義されるような状況は、じつは現代に特有の現象ではない。これまでも新技術が発明され普及することで、さまざまな表現が繰り返し革新された歴史があったことを、本書では具体的な作家や作品とともに振りかえっている。たとえば写真技術や録音技術の登場によって、絵画や音楽のあり方が大きく変化している。著者が得意とする音楽表現の変化は詳細に解説されているので、とりわけ興味深い。音楽を模倣しようとした電子機器であるシンセサイザーやサンプラーが、新しい音楽ジャンルや音楽表現を切り拓いたという。
AIを創作のパートナーにする
このように長期的な視点を持てば、人間の表現を拡張する新しいパートナーとしてAIと向き合う重要性に気づかされた。著者は、最後にAIとの付き合い方を提案している。その指針には、モノマネをさせる、間違いを大切にする、誤用するなどといったキーワードが並んでいる。どれも実用性や機能性とはほど遠い、目標設定型の研究開発とは一線を画した大胆な視点ばかりだ。
本書では表現を拡張したり、発見したりする様子を、「バベルの図書館」のなかの探索にたとえている。バベルの図書館とは、南米出身の作家ボルヘスの短編小説に登場する、ほとんど無限の蔵書をおさめた図書館のことだ。ここには、アルファベットの文字を並べた多種多様な本があるが、おなじ本は2冊ない。どの本を開いても、ほとんどのページには「MMMMMMMCV…」のような無意味な文字が並んでいる。しかし丹念に探せば、意味のある本に遭遇できるかもしれない。これを表現に置き換えると、私たちが見慣れた表現は、無数の可能性をもったバベルの図書館で発見済みの希少な本だといえる。けれども、そのほかの場所にも未知の表現がたくさん眠っている。
AIはまだ見ぬ表現の探索を助けてくれる。しかしAIの探索は、過去の表現の学習をベースにしているため限界がある。そこでAIの間違いや誤用を積極的に活用することで、探索の可能性を広げられるというわけだ。こうして発見された新しい表現は、どのように評価されるだろうか。それはきっと、それまでの文脈との差異、時代性など、ある意味で「人間らしい」文化の領域にゆだねられる。人間とAIの互いの長所をかけ合わせると、新しい文化が生まれてくるかもしれない。
本書で紹介されている数々の作品を見ていると、これまでデジタル技術とは縁のない伝統工芸のような分野でも、AI技術者と協同した新しい作品がどんどん誕生するのではないかと空想がひろがる。AIを使ったツールはどんどん身近になっているので、この数年間で新たな創作文化が大きく花開くのではないだろうか。私たちは、創作が更新されている時代に生きているのだ。そう考えると、わくわくしてくる。
本書は、AIを不気味なものとして遠ざけるのではなく、前向きな気持ちで向きあえる一冊だ。AIをつかった新しい表現への挑戦にいざなってくれる爽やかな一冊だ。ぜひお読みいただきたい。